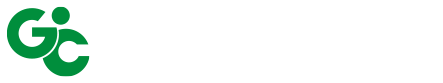東明屋諏訪神社の獅子舞
| 名称 | |
|---|---|
| 伝承地 | 箕郷町東明屋地内 |
| 期日 | 4月第1日曜日・10月第1日曜日 |
| 概要 | 東明屋獅子舞の起源は文献等がなく、定かではないが、永禄6年(440年前)武田信玄が箕輪城主の長野氏を滅ぼし箕輪城を治めた。その後武田の守護神である諏訪神社を建立し民生安定と神事芸能として、この獅子舞を奉納させたのが始まりと伝えられている。 当獅子舞は他に類がなく曲目の中に岡崎の名が出てくるところを見ると、徳川時代の四天王と称された伊井直政公が箕輪城主として最後の城主を治めたことから、この時に徳川に崇高を持たせるため格式の高い特別の宝生流に着替えをされたとも考えられる。よって、気品に溢れ、格調の高い舞で数少ない流派として文化的価値の高いものとされている。 特徴としては獅子舞の鼻頭に亀甲型の彫刻がされ、頭には山鳥や雉の尾羽等で飾られ勇壮で、貫禄のある獅子頭であり、他には見られない。 そしてカンカチ、大黒の履くわらじは黄金の二枚底と定められている。舞の振り笛の調べは悠長であるが、冴えの良い腰太鼓の音で引き締めた品の良い獅子舞であり、普通の獅子舞はカンカチと三頭獅子の四人で舞うのが一般的であるが、当獅子舞はその他大黒、ササラ振り、お稲荷様が加わり、二名の棒使いが演舞場所を清めた後で大きなナギナタを持った天狗の見守る前でこの七人が演舞されるところが大きな特色である。舞は春秋の村祭りには五穀豊穣、悪魔退散、天下泰平、子孫繁栄を祈願して神社へ奉納されその後村内一巡して各所で舞を演じている。 外部的には各祭りや小学校施設等の慰問や大会にも参加している。 【東明屋諏訪神社の獅子舞】高崎市 練習日:東明屋集会所にて第一土曜日・第三土曜日実施 |
| 周辺地図 |
箕郷町東明屋135-3(東明屋集会所) |
| 交通アクセス | 高崎駅から群馬バスの箕郷ゆきを利用、約40分で箕郷バスターミナルに到着、徒歩で25分。箕郷バスターミナルから群北第一交通の渋川ゆきバスを利用した場合は、東明屋バス停まで約3分、下車徒歩2分 |
| お問い合わせ | 石原敏明(保存会会長) 027-371-7907 |
| link |