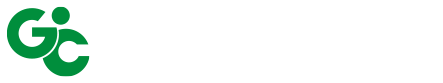上芝の八木節
| 名称 | |
|---|---|
| 伝承地 | 箕郷町上芝 |
| 期日 | 中断中(不定期) |
| 概要 | そもそも八木節の発祥は、大正年間初期に栃木県の八木宿だと伝えられており、当時東北地方から集団で出稼ぎにきていた女工達が、遠い故郷を偲んで口ずさんでいたのを、八木節の祖である「堀込源太」が民謡化したものだと言い伝えられている。 それを、街道筋の馬方衆が、カイバ桶を叩きながら唄うようになり、栃木県西部から群馬県東部へと一気に広まり、一時は出雲の「安来節」、佐渡の「佐渡おけさ」と並んで三大民謡の一つと言われた時期もあったと言うことである。 上芝に伝わったのは、大正年間の中期頃、当区に住む「神沢守明」さんが、出稼ぎの仕事先で覚えたものを持ち帰り、当時の若い衆に教えたのが始まりである。 また、その後、元祖の「堀込源太」が弟子に後を継がせて、隠居の身で当地に来て、泊り込んで教え込んだ元祖直伝の芸だと伝えており、それ故か当区の保存会では、現代風にアレンジした踊りで無く、かたくなに昔のままの踊り方に徹している。 囃し方も、他所では和太鼓やドラムなどを使っているところもあるが、上芝八木節保存会では昔ながらの酒樽に太鼓(おおつづみ)、笛に摺り鉦だけで囃している。踊り方も、手拭い踊りに花輪踊りの女踊りと、菅笠と日傘を使った男踊りの、四通りの踊りで構成されている。八木節音頭においては、昔から伝わる「紺屋高尾」、「鈴木主水」と云う艶ものや「国定忠治」、「乃木将軍と辻占ら売り」の伝記もの、また、「継子太郎」と云う人情物等があるが、当保存会では、昭和52年に当区在住の「関口連蔵」さんが作詩した、歴史に残る箕輪城の築城から落城に至るまでを唄いこんだ「ああ箕輪城」だけに絞り現在に至っている。このような保存継承の努力が認められ、平成7年3月に箕郷町教育委員会より「箕郷町民俗文化財」に指定された。 【上芝の八木節】高崎市 |
| 周辺地図 |
箕郷町上芝 |
| 交通アクセス | 群馬バス(箕郷営業所ゆき)高崎駅より約35分、 四ッ谷バス停で下車、徒歩3分。 |
| お問い合わせ | 箕郷町第15区区長が保存会長を兼務している。 |
| link |