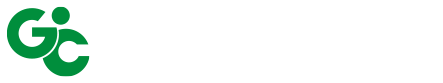桐生木遣
| 名称 | |
|---|---|
| 伝承地 | 桐生市 |
| 期日 | 不定期 |
| 概要 | 労働歌であった木遣歌が現在の形に体系づけられたのは、鳶を主体とした火消しが組織された享保年間(1716)の頃と言われている。桐生においても江戸からの町人文化の流入とともに、鳶や火消しは桐生新町の自治組織に組み入れられ定着していった。桐生の木遣は、江戸の指導者である「西行」によって伝授されたと言われているが、江戸木遣の大間に対し、テンポが速い典型的な中間となっておりこれが特徴となっている。木遣歌は口伝によって受け継がれ成熟していったものであるが、独特な高尚の節回しと、自在で奥ゆかしい響の詞とともに斬新で洗練された裳束による粋といなせの姿で、祭事や各種慶事に披露されることも多く、桐生木遣として継承された45曲のうち、完全に伝わるものは26曲である。 平成元年(1989)桐生市指定重要無形民俗文化財。 【桐生木遣】桐生市 |
| 周辺地図 |
桐生木遣 |
| 交通アクセス | 開催場所により異なる |
| お問い合わせ | 桐生市教育委員会文化財保護課(0277-46-6467) |
| link | 桐生市ホームページ |