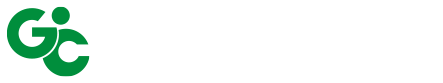中栗須神明宮獅子舞
| 名称 | |
|---|---|
| 伝承地 | 中栗須 |
| 期日 | 10月17日に近い日曜日 |
| 概要 | 神明宮の獅子舞は、口伝によると阿久津の獅子舞の流れから来ていると言われている (現高崎市阿久津町)。その年代は獅子頭を納める長持ちの蓋に、正徳二年(1712)に造るとある。平成24年で300年になる。 当地中栗須には「神明宮」と「諏訪神社」の二社があった「太々神楽」は神明宮の祭典に奉納し「獅子舞」は村の西方、小字諏訪地内の諏訪神社の祭典に奉納したと云う。 明治新政府の方針で一村一社の「御触れ」により合祀し、中栗須は「神明宮」として、春祭りは「太々神楽」秋祭りは「獅子舞」と氏子の努力により現在まで継承されている。 尚、獅子を出すには費用がかかるので、その年に病気が流行したとか、養蚕が不作、稲作の不作等の年には式典のみで、獅子舞の奉納はなかったとのことである。 昭和52年(1977)獅子舞についての打合せ会議(世話人・区長・保存会員)で時代の移り変わりと共にこのままでは継承者が減少してしまうのではと言う事で、以降毎年奉納することに決まった。 流派は稲荷流。ラ行派である。 演目は、「打揃い」「道下り」「おかざき」「諏訪様のスリ込み」「二上がり」など。 【中栗須神明宮獅子舞】藤岡市 |
| 周辺地図 |
中栗須(神明宮) |
| 交通アクセス | |
| お問い合わせ | |
| link |