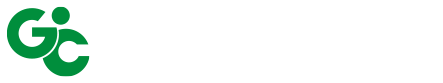稲荷流森獅子舞
 令和6年9月29日(日)『受け継がれる群馬の獅子舞』開催時写真
令和6年9月29日(日)『受け継がれる群馬の獅子舞』開催時写真
| 名称 | |
|---|---|
| 伝承地 | 森 |
| 期日 | 3月15日に近い日曜日(森飯玉神社春季例大祭) |
| 概要 | 1712年3月15日(正徳2年)、当時森村神宮であった塚越大和守正屋は、稲の精霊とされる穀物の神様である「倉稲魂命」を祭神とする神社の建立を時の中御門天皇に申し出て裁許状を下賜され、塚越家の所有地である森村飯玉久保にお宮を安置し、飯玉大明神と命名した。大明神の神前には村民が五穀豊穣と無病息災を祈願する姿が絶えなかったそうである。 1750年4月、隣村の神明宮の春祭りで神楽や獅子舞を見るにつけ、森村も獅子頭を購入して大明神に奉納しようと気運が高まり、村民が出し合った金子を元に、村役が内山峠を越えて信州佐久から獅子頭を購入し、舞形や笛は和紙に認めていただき、近隣師匠の応援を得て1751年3月15日の大明神の春祭りで獅子舞を奉納したのが始まりである。以来、江戸時代から明治、大正、昭和と受継がれ、本年で265年の歴史を刻む。 流派は「稲荷流」で、カンカチ1人、前獅子(雄)1人、中獅子(雌)1人、後獅子(雄)1人の4人構成で舞を行う。舞は全部で27舞ある。 獅子頭は当初の物と平成19年に新調した物と2組ある。 全て漆塗りで髪の毛は馬の毛である。 昭和12年から昭和21年まで時の大戦により休止となっていたが、 昭和22年、獅子舞の経験者である針谷弁三氏を師匠として青年団を中心に復活した。 昭和50年からは、森子供育成会の協力を得て、従来の仕来りを排除して希望する子供達全てに舞や笛を伝授している。 演目は、「振込」「ヤレンツウロン」「岡崎」「平庭」「花スイ」など。 藤岡市指定重要民俗文化財(令和7年3月26日指定) 【稲荷流森獅子舞】藤岡市 |
| 周辺地図 |
森(飯玉神社) |
| 交通アクセス | JR八高線 北藤岡駅から徒歩5分 |
| お問い合わせ | |
| link |