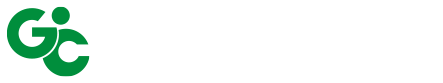藤木神楽
| 名称 | |
|---|---|
| 伝承地 | 藤木 |
| 期日 | 隔年10月第1土・日曜日 |
| 概要 | 江戸時代中期に越後のある村が飢饉のため村有神楽を売りたいと申し出た。藤木村の原地区に神明宮があり、この神楽は天照皇太神に仕える獅子であるとの越後民の言い伝えから原地区が買い受け独自で伝承させてきた。明治になり国から神社の統廃合が出され、その第一段階として各地区に存在する鎮守様の名簿を提出することになった。原地区の住民はこの神明宮が極微小の社のため、廃社命令となってしまう事を恐れ登録せずに温存した。結果、藤木村の白山様に隣村の諏訪様や熊野様等が合祠され、西小野神社として統合改名された。後にこの通達が一段落したところで原地区の住民は、神明宮を独自で維持するには経済的に苦しい事から藤木村全体に同意を得て西小野神社境内の片隅に仮社を建立し、神明宮を遷移させ事無きを得たのである。その頃藤木村には大変な疫病が入り込み、何とか鎮静化したかった藤木の民は、白山様の神楽をにえとして差し出すことに決した。白山様の神楽は現存の藤木神楽より2廻り程大きく重く、誰も振る人が無く滅亡寸前だったが、これだけでは疫病を鎮めてもらえぬと考えた藤木村民は、村のもうひとつの芸能である人形浄瑠璃もにえとして差し出した。そして疫病は鎮まったが白山様の神楽と人形浄瑠璃を失った藤木村は神明宮の神楽を西小野神社に奉納することにしたのである。 【藤木神楽】富岡市 |
| 周辺地図 |
藤木 (西小野神社) |
| 交通アクセス | |
| お問い合わせ | |
| link |