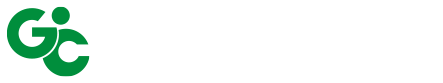国衙獅子舞
| 名称 | |
|---|---|
| 伝承地 | 松井田町国衙 |
| 期日 | 中断中(不定期・10月中旬) |
| 概要 | 国衙獅子舞は、流派は、稲荷流天下一角兵衛派と言われる。稲荷流は、京都が発祥とされるが、国衙に伝わったのは、甘楽郡秋畑からという言い伝えがある。 いつ頃から伝えられたかはっきりした記録は無いが数百年の伝統があると言われている。幕末の文久2(1862)年9月1日安中藩内各村より数十組の獅子舞が参加競演して城内で舞を披露したとき、国衙の獅子舞が見事なため、藩主板倉勝殷侯から今一度舞うように求められ大いに面目を施したと伝えられている。 また、天保11年と明治4年の「祭礼餞受納覚帳」が残されており、これによると近隣の村々からも多くの餞(寄附)が寄せられており、国衙の獅子舞が近隣でも有名だった事が窺える。 演目は、花吸い、剣の舞、オカザキ、泥鰌ふみ。 【国衙獅子舞】安中市 |
| 周辺地図 |
松井田町下増田 津雲神社 |
| 交通アクセス | |
| お問い合わせ | |
| link |