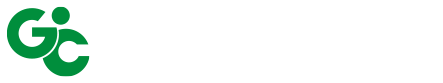かんかん踊り
| 名称 | |
|---|---|
| 伝承地 | 大字乙父 |
| 期日 | 不定期 |
| 概要 | 昭和34年8月1日から4日まで、群馬県教育委員会と上野村教育委員会が共催して上野村の民俗調査をした。そのとき民俗芸能を担当された萩原進先生が意外な収穫の一つはかんかん踊りと、かんかん節と呼ばれる清楽であったと報告されている。 かんかん踊りは文政3年(1806)江戸で大流行し、子供達が踊り狂い、その絵と歌の文句が売り広められたと言う。 かんかん踊りの起源について二つの説を上げている。 その一つは長崎の福済寺と言うお寺で、盆中、唐人やオランダ人が集まって、酒宴の席で酔いに乗じて唱歌を発し銘々踊って国元の亡魂に手向けて回向するものだと言う。 いま一つは唐船がつつがなく長崎の港に着岸すると船に祭っておいた船玉を持ち出し、陸に飾って一同唱歌を発してかんかん踊りを踊って、無事を祝して船玉に感謝したのだと言う。 また、かんかん踊りは昭和35年12月13日、NHK主催の群馬県民俗芸能大会に出演して、好評を博して広く知られるようになった。 【かんかん踊り】上野村 |
| 周辺地図 |
大字乙父 |
| 交通アクセス | 上信越自動車道 下仁田インターから車で35分 |
| お問い合わせ | 上野村教育委員会(TEL 0274-59-2657) |
| link | (動画)かんかん踊り |