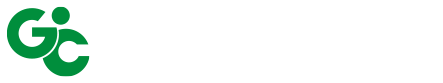役原獅子舞
| 名称 | |
|---|---|
| 伝承地 | 尻高 |
| 期日 | 夏休み最終土日(諏訪神社夏祭り) |
| 概要 | 役原獅子は、室町時代、尻高城城主、尻高左馬頭重儀が役原城に隠居し、諏訪神社を建立したときに重儀が少年時代過ごした、埼玉県寄居町の鉢形城にある諏訪神社に伝わる獅子舞(遠州流獅子舞)を習わせ、一族の繁栄と領民の安泰を願う氏神として祭ったのが始まりと言われている。尻高城、役原城も真田軍の攻撃を受け落城、集落も戦禍に会い、獅子舞も途絶えた。 その後江戸時代になり、旗本領となったが領主の肝いりで、獅子舞が復興され、諏訪神社に五穀豊穣、悪魔退散、 氏子安泰を願って奉納され現在に至って居る。 今の獅子頭は徳川末期の弘化3年(1846年)に作られたものである。 獅子舞は大太鼓をつけた頭、笛吹三人、万燈及び太鼓を持った三人の獅子(これを先獅子、中獅子、後獅子とよび、中獅子は牝獅子といわれている)、それに「ささら」という竹の楽器をもった踊り子を各獅子に組ませ、舞を賑やかにしている。昔はそれに「ひょっとこ」と「おかめ」の面をつけた二人が舞の間合いを踊りつないで、獅子舞を更に賑やかにしていた。 演目は、「七道」「前庭」「後庭」。 昭和40年6月1日 高山村重要無形民俗文化財指定 【役原獅子舞】高山村 |
| 周辺地図 |
浅間神社 |
| 交通アクセス | |
| お問い合わせ | |
| link |