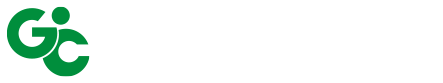| 概要 |
明治42年2月武尊山の麓、川場村萩室に建物名方命(たけみなかたのみこと)外5社を産土神(うぶすなかみ)として祀る諏訪神社が建立され、川場村の指定村社とされていた。その諏訪神社の祭礼に欠かすことのできない神事として萩室の獅子舞が今に受け継がれている。この獅子舞の起源は江戸時代初期の延宝年間(1673~80)に遡ると云われている。時の沼田城主、真田伊賀守(さなだいがのかみ)が百社建立の際、正一位諏訪大明神として御社料十二石を賜り、延宝2年(1674)10月4日の城主参詣の折、獅子舞の獅子頭3頭を奉納し以後、城主及び代参あるときは境内にて獅子舞を行うことを例とした。舞は「天下一非鋏流(てんかいちひばさみりゅう)」と称し、その起源は不明、古老によれば南北朝時代の中頃に生まれたと云われている。明治時代より農家の男衆が旧盆明け頃から夜稽古に励み、次代の子どもたちに伝えていたが昭和42年を最後に途絶えていた。近年地元での復活の声が高まり、平成3年の川場村と世田谷区縁組協定10周年事業開催に際し、復活の動きが活発化されたものの実現には至らなかった。その6年後の平成9年に有志十数名が集まって萩室獅子舞保存会が誕生、4月から獅子舞の練習が開始され10月の秋祭に実演され30年ぶりの復活を遂げ今日に至っている。演目は、庭見之段、霧獅子之段である。【萩室獅子舞】川場村 |