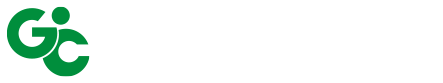貝沢西組の獅子舞
| 名称 | |
|---|---|
| 伝承地 | 貝沢町 |
| 期日 | 10月19日前後の日曜日 |
| 概要 | 起源は、不詳であるが文政3年(1820)と云われており、天保8年(1837)に獅子舞奉納の款書・届書の古文書がありおよそ200年前から獅子舞が伝承されていた事がわかる。貝沢には、西組と東組の流派の異なる獅子舞があり、当西組は、鎌倉流、東組は稲荷流でいつも競い合っていた。 西組の流派の鎌倉流の由来は、五霊神社の祭神の鎌倉権五郎景政の「鎌倉」をいただき流派の名前としたと云い伝えられている。 村社五霊神社には、「悪霊退散・家内安全・五穀豊穣」を祈念することを目的として奉納してきた。いずれも氏子によって組織され、演舞者は氏子の中の長男から選抜されて伝統が引き継がれてきたが、現在は、自由になってきた。 又、西組の獅子舞は勇壮でかつ品格があると近隣にその名をうたわれていた。 演目は、「道中しゃぎり」「大門掛り」「橋掛り」「まきだし」「にこみ」「岡崎」「くり」「岡崎くずし」。 【貝沢西組の獅子舞】高崎市 |
| 周辺地図 |
貝沢町332 五霊神社 |
| 交通アクセス | |
| お問い合わせ | |
| link |