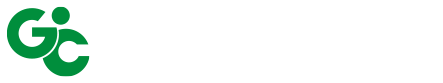飯塚獅子舞
| 名称 | |
|---|---|
| 伝承地 | 飯塚町 |
| 期日 | 4月8日(春祭)・10月19日(秋祭)の後の、直近日曜日。午後2時から。 |
| 概要 | 高崎市飯塚町に常福寺という古い寺があり、戦国時代の飯塚城跡に建っている。この寺の参道脇と村里をはなれたところに2つの薬師堂がある。 そして飯塚城跡のすぐ隣に飯玉神社があり、この神社は、旧上飯塚村・下飯塚村の総鎮守である。 毎年4月8日の両薬師如来の祭り直後の日曜日、10月19日の飯玉神社の例大祭直後の日曜日に獅子舞を奉納している。 飯塚町には、長泉寺という寺があり、江戸時代にこの寺の和尚(大臥佑道師や機外了禅師)が寺子屋の子ども達に獅子舞を指導したのが始まりといわれている。長泉寺で行われていた獅子舞が、その後、飯玉神社の祭礼に奉納されることになった。その発端は天明年間のことであるといわれている。 飯塚の獅子舞は、稲荷流。三頭の獅子(法眼・中獅子・後獅子)と冠勝(カンカチ=天狗)、大黒天、そして二人の棒遣い(赤鬼・青鬼)の七人構成。かつてはこのほかに法螺貝を吹く山伏がいた。獅子は太鼓をたたき、冠勝はカネの棒を打ち鳴らし、大黒天は軍配と枡を持って世の雑事の調停にあたる。棒遣いは露払いの役で先頭に立つ。現在、法螺貝は保存会の役員が吹いている。地域の五穀豊穣、災厄退散を祈念して舞っている。 今日、「梵天がかり」「花吸い」「三拍子」「新きり」「剣の舞」「網きり」「女獅子がくし」の7つの演目と48種の曲目が伝わっている。棒遣いには5種類の棒術が伝わっている。 平成23年4月20日 高崎市重要無形民俗文化財指定 【飯塚獅子舞】高崎市 |
| 周辺地図 |
飯塚町544(飯玉神社) |
| 交通アクセス | JR北高崎駅より徒歩16分 |
| お問い合わせ | |
| link |