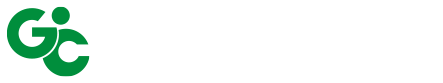烏子稲荷神社太々神楽
| 名称 | |
|---|---|
| 伝承地 | 上小塙町 |
| 期日 | 4月第1日曜日・10月9日 |
| 概要 | 烏子稲荷神社の太々神楽の起源は、 元禄2年(1689) に神主の山田和泉守の次男である山田権平藤原秀基を新宅に出す際に太々神楽の主人となってこれより先、 引き継いでいくようにと命じた記録が残されている。また、永禄6年(1563)に武田信玄が箕輪城を攻略後に新しく社殿、 神楽殿を造営したことが古文書に書き記されている。 しかし、伝承ではさらに古く、鎌倉・室町時代まで遡ると伝えられている。 昭和の前半までは3月15日の春祭りで3日間神楽の奉納が行われ、地元の人たちや他地域からたくさん人が参拝に来て、 大変賑わっていたという。 当時の演目は36座あったが、 現在と座数の数え方が異なるので比較できないが半数が継承されてきた。 現在継承されている演目は先代の人たちの知恵により見事に現在に合うよう凝縮され、 コンパクトに構成されている。 その構成は大きく分けて式舞と興舞と稲荷神 (宇迦之御魂命) の3部からなる。 【烏子稲荷神社太々神楽】高崎市 |
| 周辺地図 |
上小塙町564 (烏子稲荷神社) |
| 交通アクセス | |
| お問い合わせ | 高崎市総務部文化課(TEL 027-321-1203) |
| link | 高崎市ホームページ |