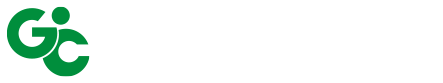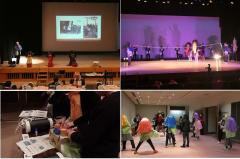伝統文化レポート
- 2024/07/13
- 県内大学連携伝統文化の魅力発信・啓発事業 群馬県立女子大学群馬学センター地域連携事業 ぐんまの民俗芸能 in 県立女子大 vol.2 ~人形浄瑠璃~
第48回県民芸術祭参加事業 県内大学連携伝統文化の魅力発信・啓発事業 群馬県立女子大学群馬学センター地域連携事業 ぐんまの民俗芸能 in 県立女子大 vol.2 ~人形浄瑠璃~ 7月13日(土)、群馬県立女子大学 講堂にて開催されました。
はじめに、群馬県立女子大学群馬学センター 簗瀬大輔教授によるレクチャー「浄瑠璃王国・ぐんまの文化力」にて群馬県内の人形浄瑠璃の歴史等についての説明が行われ、続くワークショップでは八城人形城若座のみなさまが実際の人形の仕組み・操作方法などを解説後、来場した学生が実際に3人で力を合わせて「3人遣い」の人形操作を舞台上で体験、披露いたしました。最後に、座員のみなさまによる「生写朝顔話 宿屋の段~大井川の段」が上演され、盛大な拍手が送られました。「長年群馬に住んでいながら郷土芸能に人形芝居があることを知らなかった」との声も多く、「浄瑠璃の歴史から人形の仕組み・操作も非常にわかりやすく、城若座の皆さまの熱意が感じられる公演、すばらしかった、心豊かになった」との声も聞かれました。終演後には人形や三味線の体験会も行われ多くの来場者が参加いたしました。はじめは実際の人形や楽器を前に緊張している様子も見受けられましたが、「触ってみてすごく興味を持った、人形の構造や作り方を調べてみたくなった、感動した!」等、実物に触れ楽しむ来場者が多く、予想以上の盛り上がりを見せていました。
writer: 事務局
- 2024/02/25
- 令和5年度 ぐんま伝統歌舞伎の祭典
第47回県民芸術祭参加事業 令和5年度 ぐんま伝統歌舞伎の祭典が、2月25日(日) 吉岡町文化センター ホールにて開催されました。
渋川子ども歌舞伎による「鎌倉三代記 絹川村閑居の場」、群馬県伝統歌舞伎保存協議会による「奥州安達ヶ原三段目 袖萩祭文の場」が上演されました。渋川子ども歌舞伎は小学生から高校生が出演、「子どもの演技に関心・感動した、大人顔負けの熱演で将来が楽しみ」との感想が多く寄せられ、今後の活躍がより一層期待される迫真の演技が繰り広げられました。後半は県内で活動を続ける「赤城古典芸能保存会」「半田歌舞伎坂東座」「渋川歌舞伎」「平出歌舞伎保存会」「横室歌舞伎保存会」の5座が加盟する群馬県伝統歌舞伎保存協議会のみなさまが出演いたしました。「皆さんで作り上げているのが分かり、伝統を受け継いでいる姿に感銘した、これからも応援したい」「黒子、早わざで変身させて素晴らしかった」「生の歌舞伎を初めて見ました。大変素晴らしく感動しました。」等、今を生きる歌舞伎の世界を存分に楽しむ来場者の様子が伺えました。当日はみぞれがちらつく大変寒い日でしたが、約300名の来場者が足を運び、4年ぶりに販売が行われたお団子やコーヒー等も完売し、盛大な祭典となりました。
writer: 事務局
- 2024/01/21
- 令和4年度第二次補正予算事業 地域における子供たちの伝統文化の体験事業 「獅子舞ワークショップ」
令和4年度第二次補正予算事業 地域における子供たちの伝統文化の体験事業
「獅子舞ワークショップ」が、1月21日(日)に甘楽町文化会館で開催されました。
当日は雪の予報もあり天候が心配されましたが、県内各地から約20名の参加者が集まり、講師の「諏訪神社天引獅子神楽保存会」のみなさまの指導のもと、大変賑やかに行われました。「地域の伝統を守る活動やその歴史、踊りの意味など学べて勉強になった」「自分で作った獅子頭で踊れたのが楽しかった、小学生のこどもでも楽しく取り組めた」との感想や、「また参加したい」「発表も楽しかった」との声も多く聞かれ、獅子舞を通して伝統芸能に興味を持つきっかけとなり、大変充実した時間となった様に感じられました。
writer: 事務局
- 2024/01/14
- 令和4年度第二次補正予算事業 地域における子供たちの伝統文化の体験事業 「歌舞伎化粧体験」
令和4年度第二次補正予算事業 地域における子供たちの伝統文化の体験事業
「歌舞伎化粧体験」が、1月14日(日)渋川公民館 講堂で開催されました。
小学生と保護者ら30人が歌舞伎のメイクに挑戦しました。とても人気があり、早くから予約でいっぱいとなり当日を迎えました。講師は市川鏡十郎社中の3名にお願いいたしましたが、「先生の説明が丁寧で分かりやすくて楽しめた」との声が多く、また、「改めて歌舞伎を見てみたいと思った」「メイクができて楽しかった、嬉しかった」「また参加してみたい」と、大好評のうちに終了いたしました。
writer: 事務局
- 2023/12/10
- ぐんま伝統芸能ワークショップ(神楽)
第47回県民芸術祭参加 令和5年度伝統文化継承事業
ぐんま伝統芸能ワークショップ(神楽)が、12月10日(日)、前橋市総社公民館 ホールで開催されました。
講師の「植野稲荷神社太々神楽保存会」のみなさまによる神楽解説、舞の実演鑑賞、そして、参加者各々が作成したオリジナルの狐のお面をかぶり、豊作を喜び狐が楽しく舞う「二ツ狐」の舞を体験いたしました。また、本物の神楽面の展示や実際にかぶる機会も設けられ、大変貴重な時間となり、伝統文化が自身の文化として身近なものに感じられ、今後、地域のお祭りなどに積極的に参加してみたいとの感想・抱負も聞かれました。伝統文化を続ける事の大切さ、これまで刻んできた歴史の重さ、素晴らしさを感じるワークショップとなりました。
writer: 事務局
- 2023/12/07
- 県内大学連携伝統文化の魅力発信・啓発事業 =共愛学園前橋国際大学公開授業=「人間を考える 」~ぐんまの郷土芸能 人形浄瑠璃~ ー英語・日本語字幕付ー
第47回県民芸術祭参加事業 県内大学連携伝統文化の魅力発信・啓発事業 =共愛学園前橋国際大学公開授業=「人間を考える 」~ぐんまの郷土芸能 人形浄瑠璃~ ー英語・日本語字幕付ー12月7日(木)共愛学園前橋国際大学 5号館 5101 KYOAI COMMUNITY HALLにて開催されました。
昨年に引き続き、八城人形浄瑠璃「城若座」のみなさまにより、人形の説明、日本語・英語字幕付き公演「傾城阿波の鳴門 順礼歌の段」、体験学習と続き、学生さんを中心に人形芝居の魅力に引き込まれました。
人形の操作体験では、たくさんの学生さんがとても楽しそうに動かす姿が見られました。想像以上に細かい繊細な動きに驚く学生さんが多く、また、義太夫と三味線と人形の動きがピッタリと合い、人形が表現する人の感情に触れる事が出来た、外国の方にも日本の文化として是非知ってもらいたいとのご意見も聞かれました。
writer: 事務局
- 2023/12/02
- 県内大学連携伝統文化の魅力発信・啓発事業 =群馬県立女子大学群馬学センター連携事業 県民公開講座=~ぐんまの郷土芸能 人形浄瑠璃~
第47回県民芸術祭参加事業 県内大学連携伝統文化の魅力発信・啓発事業 =群馬県立女子大学群馬学センター連携事業 県民公開講座=~ぐんまの郷土芸能 人形浄瑠璃~ 12月2日(土)、群馬県立女子大学 講堂にて開催されました。
「下牧人形芝居保存会吉田座」のみなさまによるワークショップの後、「寿式三番叟」、「傾城阿波の鳴門 順礼歌の段」の上演と続き、学生から70代以上の大人まで幅広い入場者が郷土芸能である人形芝居を体験・鑑賞いたしました。
ワークショップでは初めて人形を手にし、感情表現の所作や、3人での動きの連携の重要性を感じたり、男性と女性の人形の特性、また、着物にまで想いを馳せ、人形が生きているかの様で職人技と感じた等、多くの方が興味を惹かれ、感動の1日となりました。
writer: 事務局
- 2023/12/03
- ぐんま伝統芸能ワークショップ(篠笛)
第47回県民芸術祭参加 令和5年度伝統文化継承事業
ぐんま伝統芸能ワークショップ(篠笛)が、11月12日(日)・19日(日)・26日(日)、12月3日(日)、テラス沼田6階 コミュニティテラス 音楽スタジオ、沼田市保健福祉センターで開催されました。
参加者は沼田市のみならず群馬県内の各地域から集まりました。2日目より2つのグループに分かれて練習を行い、最終日には発表会を実施、「さくら」「たなばた」「荒城の月」を演奏いたしました。講師は昨年に引き続き、ヌマタ・アート・アンバサダーでもある富澤優夏先生にお願いいたしました。「篠笛のノウハウが分かってきて、これからももっと素晴らしい音色を出せるように続けていきたい」「先生が優しくて楽しかった」また、「発表会は恥ずかしいけれど楽しかった、折角なので良い機会かと思った」等の感想が聞かれ、みなさんとても楽しそうに吹く姿が、印象的でした。
writer: 事務局
- 2023/11/03
- ぐんま伝統芸能ワークショップ 獅子舞ワークショップ
第47回県民芸術祭参加 令和5年度伝統文化継承事業
ぐんま伝統芸能ワークショップ(獅子舞ワークショップ)が、11月3日(金・祝)に美喜仁桐生文化会館(展示室)で開催されました。
当日は、本物の獅子頭の展示も行われ、各々が思い思いの獅子頭を作成後、講師の「月田近戸神社獅子舞保存会」のみなさまの実演鑑賞・体験指導を受け、汗をかきながらも楽しそうに踊る参加者の様子が見られました。参加した子どもの保護者より「一緒に舞う中で、思いがけず真剣になってしまった」との声もあり、大人から子供まで伝統文化を感じ、そして学ぶ、貴重な時間となりました。
writer: 事務局
- 2023/10/14
- 津久田人形芝居櫻座 生誕300年祭
第47回県民芸術祭協賛事業
「津久田人形芝居櫻座 生誕300年祭」が10月14日(土)、渋川市赤城町津久田桜の森八幡宮境内 津久田人形舞台にて開催されました。津久田人形舞台は文化8年(1811年)に建造された県内最古の農村舞台で、人形芝居用に工夫された舟底式の構造は大変珍しく、また、現存する人形38体と共に県の重要有形民俗文化財になっております。
当日は午前9時から開会式が行われ、津久田人形操作伝承委員会櫻座による「三番叟」、「鎌倉三代記七段目 三浦別れの段」、津久田小学校人形クラブによる「傾城阿波の鳴門 巡礼歌の段」、この生誕300年祭に合わせて結成された手作り人形劇 つ組による「モチモチの木」、津久田人形操作伝承委員会櫻座による「絵本太功記十段目 尼ヶ崎の段」、そして千秋楽・閉会式と、一日を通して盛大に執り行われ、約800人の観客が伝統のある人形芝居の世界に魅了されました。初舞台を踏んだ小学生の活躍も目覚ましく、伝統を感じられる素晴らしい一日となりました。
writer: 事務局